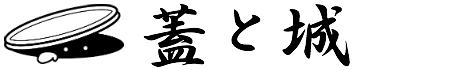滋賀県長浜市に残る石田三成関連史跡を訪れたのですが、三成が隠れたというオトチ岩窟の後に訪れたのは、関ヶ原合戦での敗戦後に三成が目指したという古橋村の法華寺三珠院(現:滋賀県長浜市)です。
法華寺三珠院とは
近江の戦国大名・浅井長政も通ったという法華寺は、近江の地侍であった石田家とも縁が深く、三成も手厚く保護をしていました。三成の居城である佐和山城には法華丸という曲輪がありますが、この法華寺が築城時に建物等を寄進したことが由来となっています。
寺内には五輪塔などが残っており、日付を見てみると江戸期のものです。三成に縁が深かった法華寺ですが、関ヶ原合戦後にも特に咎めを受けることは無く、明治維新後の廃仏毀釈も乗り切って続いていたようですが、大正期には無住となってしまっており、現在は山中に朽ち果ててしまっています。
 『三珠院跡』
『三珠院跡』
 『現在は荒れ果てている・・・』
『現在は荒れ果てている・・・』
三成はなぜ三珠院を目指したのか
関ヶ原合戦にて敗戦後に逃れるルートは限られています。揖斐川を北上するルートは険しく(小西行長はこのルートで捕縛されている)、東軍の最重要攻撃拠点である東山道から佐和山へ抜けるルートは当然取ることが出来ません。残すルートは伊吹山麓から北へ迂回するルートで、三成はこのルートを通って母親に所縁のある古橋村を目指しましたが、縁を辿っただけでは無いと私は思います。
三珠院を訪ねてまず驚いたのは寺域の広さ。最盛期には100を越えていたという塔頭がある法華寺は、中程度の城郭にも匹敵します。己高山(こだかみやま)を背後にした要害の地でもあります。荒れ果てた寺跡には石垣が何カ所か残っていますが、反りもしっかりとされている石垣などは三成の時代に改修されていると思われます。
現代の私たちは、江戸期の武士道フィルターで戦国時代の武将を考えてしまうことがありますが、戦国時代という「超現実主義」の時代に生きた武将達に、「戦場で負けて潔く散る」などという思想はありません。仮にそういった考えの武将がいたとしても少数派でしょう。三成は関ヶ原の敗戦後もあくまで再起を考えていたと思います。そして佐和山城が包囲されることが容易に予想されたときに、再起の地としてこの古橋村を選んだのでしょう。それは母の故郷というロマンティズムではなく、戦国を生き抜く大名の常識として準備しておいた支城・砦としての役割を法華寺に求めてのことなのです。
「城郭寺院」という城巡りのカテゴリーがあります。戦国時代から江戸期にかけて築城された城郭は、石垣や櫓など多くの技術を寺院建築から学んでいます。そして武装集団である「僧兵」を抱えた寺院自身もまた、抗争に堪えられるだけの防御遺構を構築していました。江戸期になっても、城下にある寺内町は有事の際には城の出郭としての役割が果たせるように配置されているのも、この城郭寺院の流れを組んでいるということです。
法華寺はまさしく三成が領国防衛の支城として改修した城郭寺院であり、ここを拠点に再起を募れば北は盟友・大谷吉継の領国である敦賀、湖北から丹後路へ抜ければ家老である嶋左近の娘婿・小野木公郷の福知山へ通じています。古橋への敗走もまた三成にとっては戦略の一つであったのです。
 『寺域は広大』
『寺域は広大』
 『法華寺の石垣』
『法華寺の石垣』
おわりに
法華寺三珠院へのアクセスは、オトチ岩窟と同じく己高庵(ここうあん)から2キロほどの山道になります。一応舗装はされた道路はありますが、荒れており道も細いので大型車や運転に不慣れな方は己高庵から徒歩で行った方が良いでしょう。夏場にはクマも出没しますし、人気はまったく無いので十分に注意して訪れてくださいね。

 『法華寺山道跡』
『法華寺山道跡』
法華寺三珠院付近の地図
三成の母親所縁の寺院。最盛期には100を越える塔頭があったという。佐和山城の法華丸は、この寺院が築城時に寄進をしたことに由来する。現在は廃寺で荒れ果てており、クマも出没するので訪れるには注意が必要。
http://jibusakon.jp/mitsunari/sanjuin
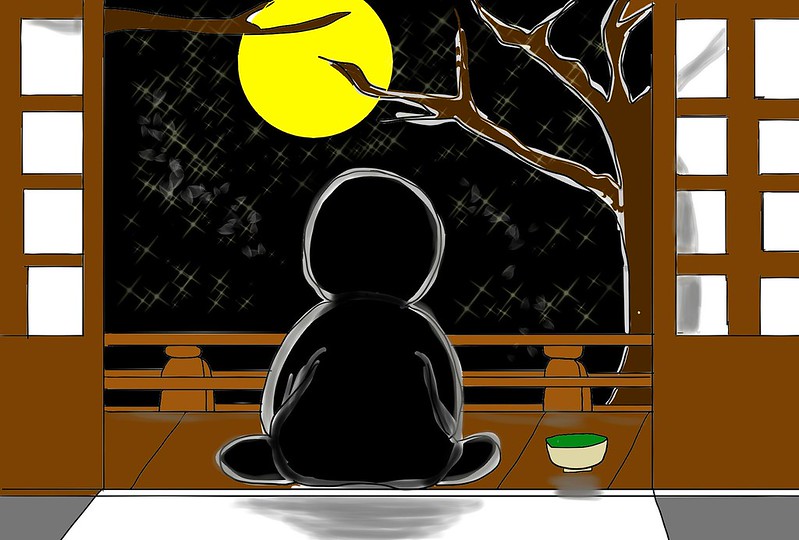
『三成はこの寺で何を考えていたのでしょうかね・・・?』